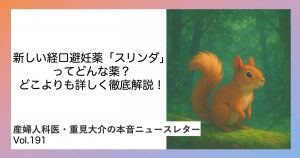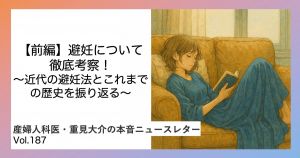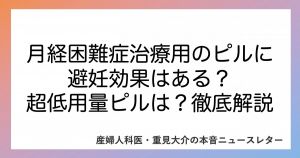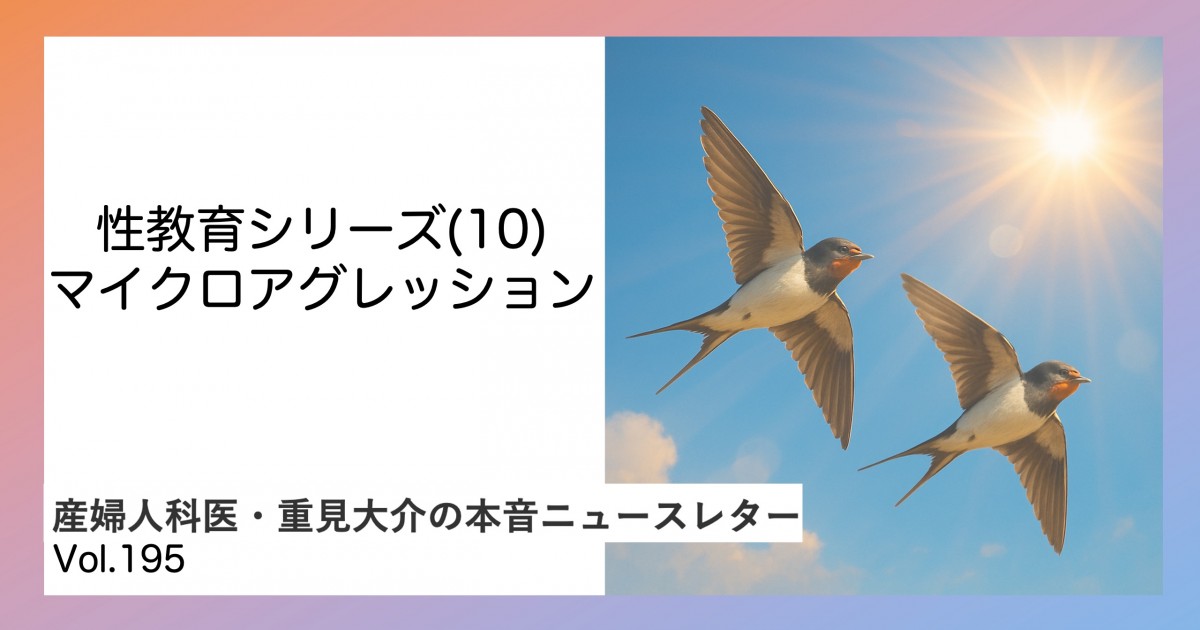政治や政策による「女性のSRHR」への影響を考える
本ニュースレターでは、女性の健康や産婦人科医療に関わるホットトピックや社会課題、注目のサービス、テクノロジーなどについて、産婦人科医・重見大介がわかりやすく紹介・解説しています。「○○が注目されているけど、実は/正直言ってxxなんです」というような表では話しにくい本音も話します。
今回は無料登録で全文読める記事です。メールアドレスをご登録いただくだけで最後まで読むことができます。
この記事を書いているのは、ちょうど2025年7月の参議院選挙の頃です。さまざまな政党や候補者が、それぞれの考えや政策を訴えています。中には、医療や健康に関するものも含まれ、医師である私にとっても大きな関心ごとです。
そこで、日本における過去50年間ほどの政策や政治的動きが、女性のSRHR(性と生殖に関する健康と権利)にどのような影響を与えてきたかについて、法律、政党の姿勢、社会運動、国際的圧力なども含め、整理してみようと思います。
文字数の都合で過去全ての事例や情報を網羅はできませんが、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。
この記事でわかること
-
SRHR(性と生殖の健康と権利)とはどんなものか
-
避妊政策の変遷:ピル承認の遅れと緊急避妊薬へのアクセス
-
人工妊娠中絶と母体保護法:法律の変遷と権利をめぐる攻防
-
性教育の推進と課題:学校現場と政治・社会の攻防
-
不妊治療支援の拡充:少子化対策と生殖医療の進歩
-
性暴力対策と刑法改正:被害者支援と司法の変革
-
社会を変えた声とこれからの課題
-
選挙に参加することの意義
-
マイオピニオン(総合的な私個人の考えや意見)
はじめに:SRHR(性と生殖の健康と権利)とは?
本記事のキーワードである「SRHR(性と生殖の健康と権利)」について、まずは解説します。ご存知の方も復習としてさらっと読んでみて下さい。
女性が自らの性や生殖に関することを自由に決定できる権利は、国際的には1994年の国際人口開発会議(カイロ会議)で明確に「人権」として位置付けられました。この権利には、避妊方法や人工妊娠中絶の利用、子どもの人数や産む時期を自分で決める自由、そして安全で満足のいく性生活を営む権利が含まれ、各国政府はその実現のために必要な手段や情報を提供する責務があるとされています。
こうした権利が保障されることで、「健康」を保ち、向上させやすくなります。こうした「自分の身体、性や生殖について、十分な情報を得られ、自分の望むものを選んで決められ、そのために必要な医療やケアを受けられる」ことを、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス&ライツ(SRHR)」と言います。
では、日本ではこのSRHRが十分に守られてきたでしょうか。残念ながら、この50年を振り返ると、日本の政治・政策は必ずしも女性のSRHR実現に積極的だったとは言えないように思えます。
例えば、避妊では男性用コンドーム頼みの状況が長く続き、女性主体の確実性の高い避妊法である経口避妊薬(ピル)は1999年にようやく承認されたものの、現在でも医師の処方箋が必要です。
また、人工妊娠中絶に関しては法律上配偶者(パートナー)の同意が原則として求められるため、必ずしも女性が単独で決められるわけではないという状況が続いています。
こうした課題は、女性の身体に関する自己決定権が十分保障されていないことを示しており、国内外から改善を求める声が上がってきました。
本稿では、過去50年間ほどに日本で起きた、女性のSRHRに影響を与えた主な政治・政策上の出来事を、避妊、人工妊娠中絶、性教育、不妊治療、性暴力対策といったトピックごとに整理していきます。
それぞれの分野での重要な法制度の変更、政党や政府の姿勢、官僚組織の対応、社会運動からの働きかけ、そして国連をはじめとする国際的圧力について概観していきます。いかに政治が私たちのSRHRに大きな影響を与えるかを知り、考えてみるきっかけになれば嬉しく思います。
避妊政策の変遷:ピル承認の遅れと緊急避妊薬へのアクセス
経口避妊薬
日本における避妊政策は、長らく男性主体のコンドームに依存しており、女性自身が主体的に使える避妊手段は限られてきました。国際的には1960年代に経口避妊薬(ピル)の使用が広まったにもかかわらず、日本では副作用への懸念や「性の乱れ」を招くという意見・価値観から、政治的にも保守的な姿勢が強く、1999年まで承認されませんでした。
とりわけ、1998年にバイアグラ(勃起不全治療薬)がわずか半年で承認されたのに対し、ピルは30年以上も認められなかったことは、「男性の快楽はすぐに認められ、女性の避妊は後回しにされた」として批判されました(この意見については、感情面をひとまず置いて冷静に考えるべきだとは思っていますが、そうした場合にも、やはり意思決定層に男性が多かったことや、企業による市場価値などの観点で、避妊薬は優先度が高まらなかったという背景はあるだろうと思っています)。
1999年にようやく低用量ピルが承認されたものの、現在でも処方箋が必要であり、費用や社会的偏見から使用率は先進国中でも最低水準にとどまっています。さらに、避妊インプラントや注射など、他国では一般的な方法が未だ導入されていません。
緊急避妊薬(アフターピル)
一方、緊急避妊薬(アフターピル)に関しても課題が続いています。性暴力や避妊失敗時に重要な手段であるにもかかわらず、日本では医師の処方が必要で、入手に高額な費用と時間がかかります。国連の女子差別撤廃委員会(CEDAW)からも、「市販薬としてのアクセス改善を図るべき」との勧告が繰り返されています。2023年にはようやく薬局での試験販売が認められる方向に進みましたが、まだ調査事業の段階で、正式に広く購入できるようになるにはまだ時間がかかりそうです。
避妊に関して日本が抱える本質的な問題
避妊に関して日本が抱える本質的な問題は、女性の身体に関する「自己決定権」が制度上、社会的にも十分に尊重されていない点です。避妊手段の選択肢が乏しい(海外では、日本で承認されていないインプラント型やパッチ型の避妊薬も存在しています)こと、女性に負担が偏りやすい構造、そして避妊に関する情報提供や性教育の不足が、意図しない妊娠のリスクを高め、結果的に人工妊娠中絶にもつながってしまっています。
今後は、避妊手段の多様化と利用しやすさの向上に加えて、若年層への包括的性教育の普及、医療従事者や薬剤師による適切な情報提供体制の整備など、社会全体で避妊に関する「選択と支援」が行える仕組みが求められています。避妊は個人の問題であると同時に、公共の健康と権利に関わる重要なテーマだということを社会全体で持っていければいいなと思っています。
*関連記事(ぜひご参照ください)
この記事は無料で続きを読めます
- 人工妊娠中絶と母体保護法:法律の変遷と権利をめぐる攻防
- 性教育の推進と課題:学校現場と政治・社会の攻防
- 不妊治療支援の拡充:少子化対策と生殖医療の進歩
- 性暴力対策と刑法改正:被害者支援と司法の変革
- 社会を変えた声とこれからの課題
- 選挙に参加することの意義とは?
- マイオピニオン(総合的な私個人の考えや意見)
すでに登録された方はこちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績