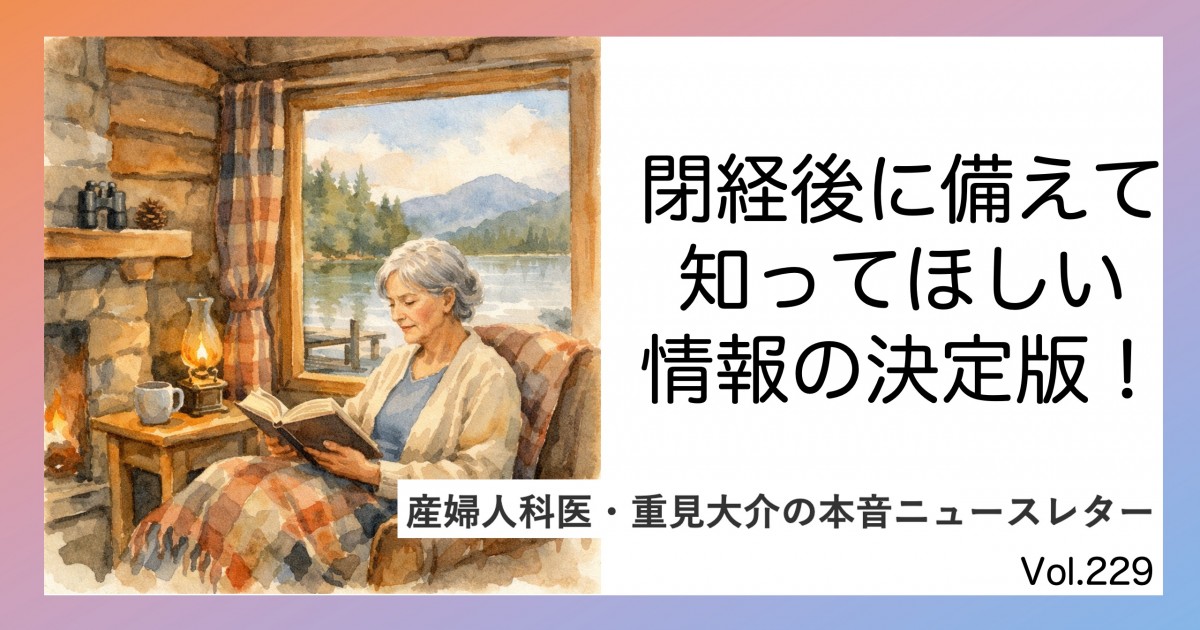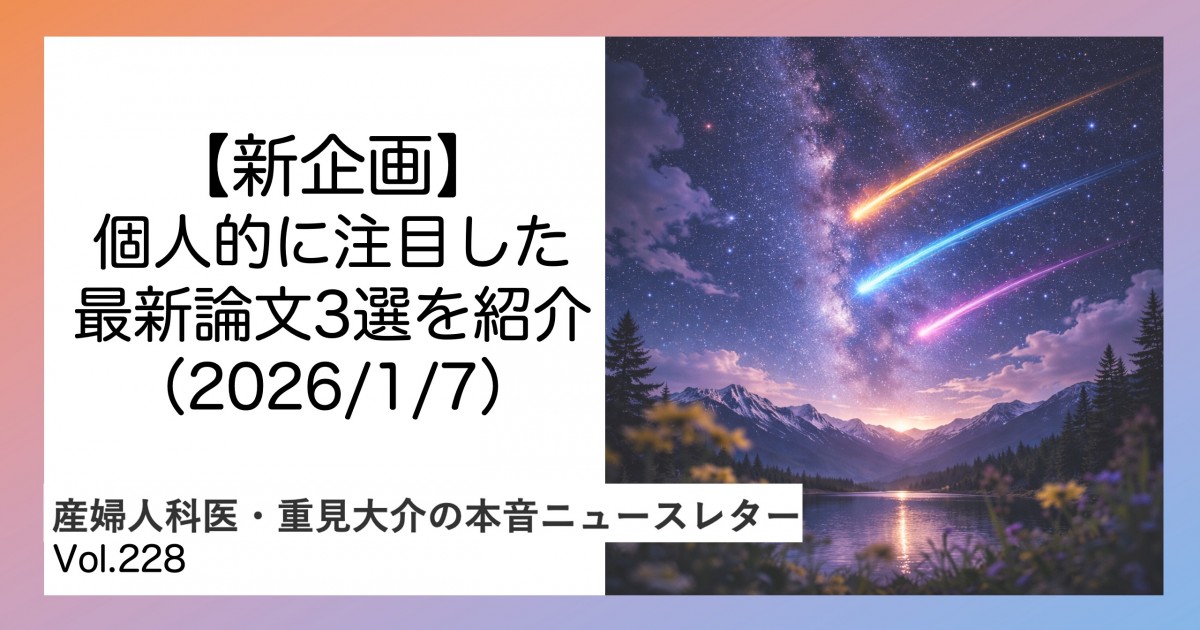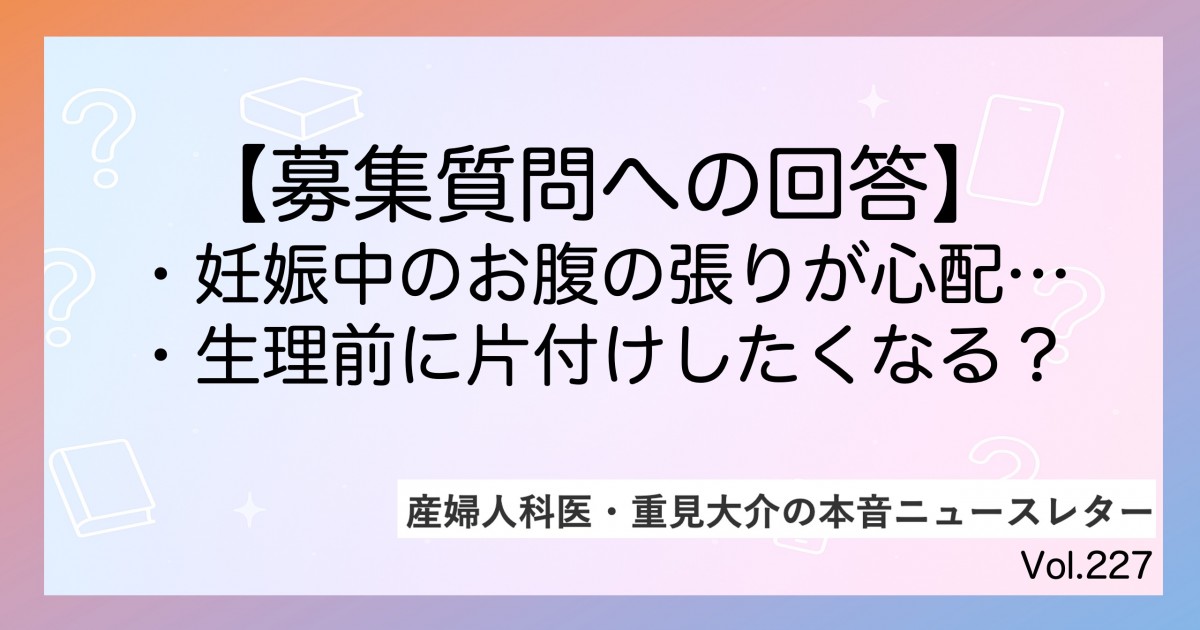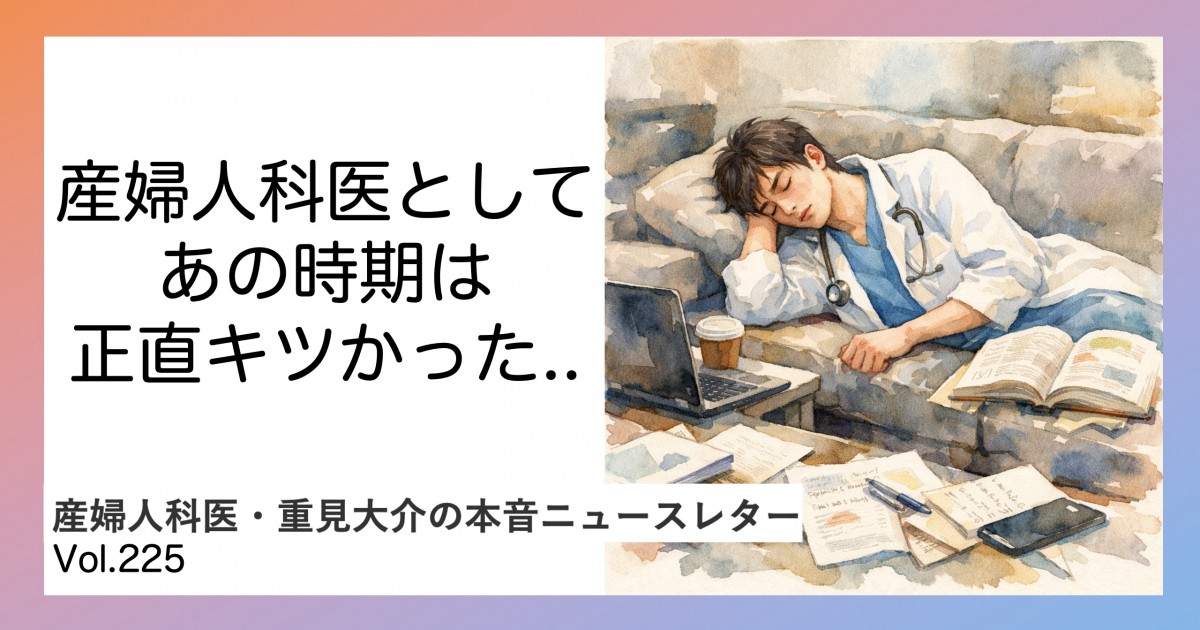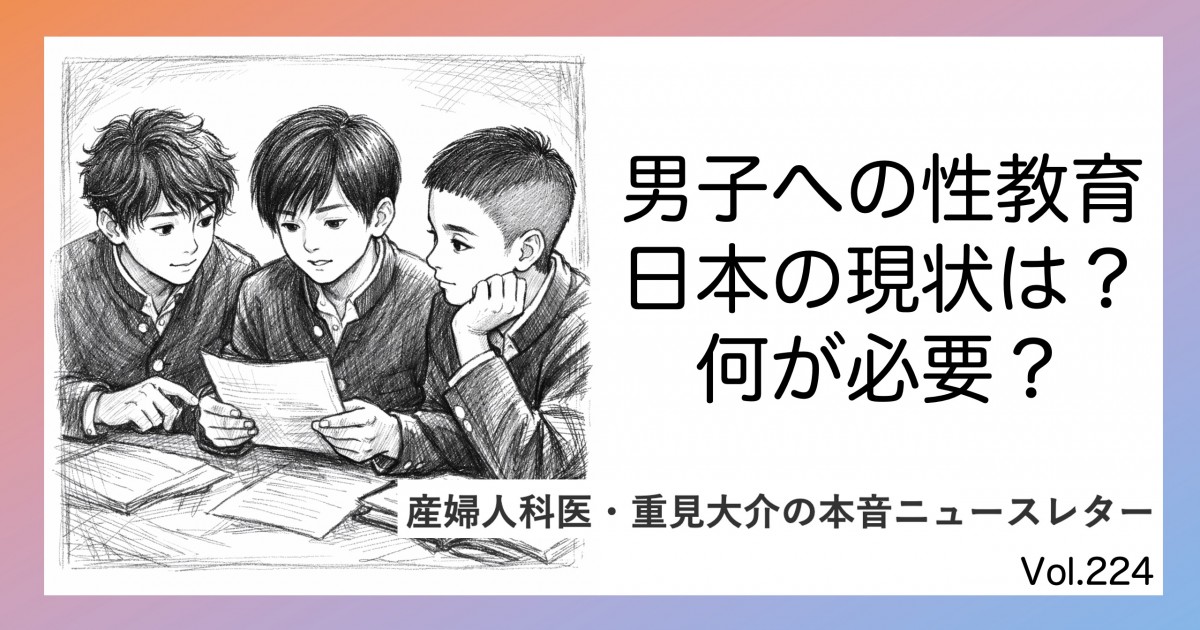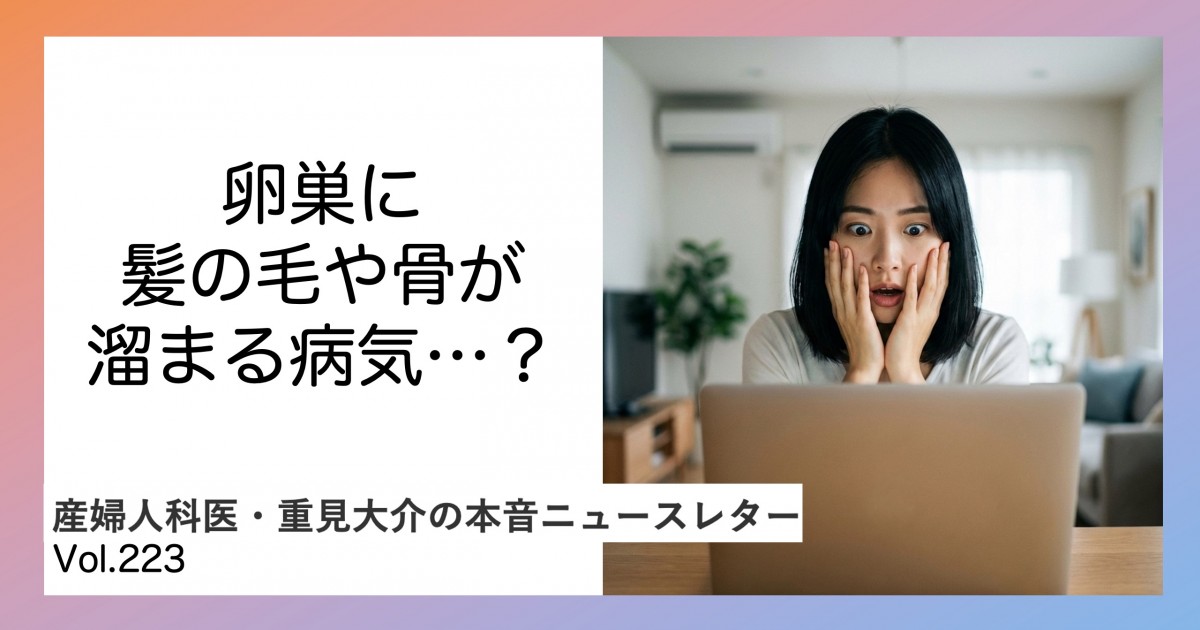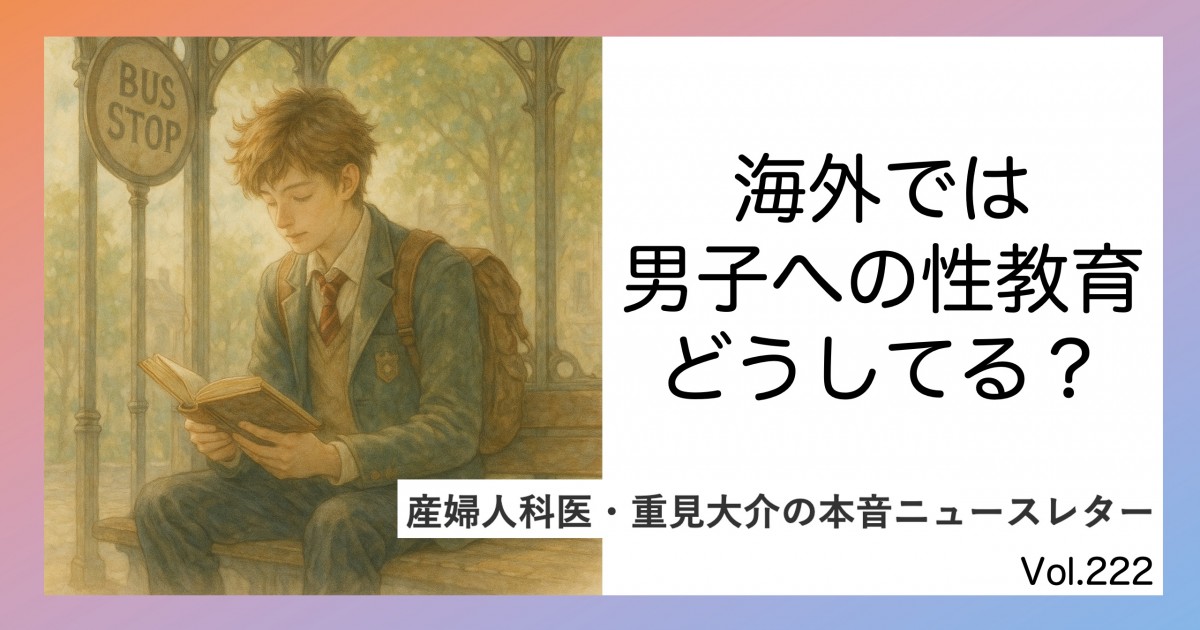更年期障害と認知症の関連 〜女性特有のリスクや注意点、対策とは〜
最近の研究結果を踏まえて女性特有のリスクや注意点、対策を解説します。
この記事でわかること
-
更年期障害とはどんな病気か
-
認知症とはどんな病気か
-
女性におけるアルツハイマー病の発症頻度
-
アルツハイマー病発症の女性特有のリスク因子
-
認知症を予防するのに有効な対策とは
-
マイオピニオン(私個人の考えや意見)
更年期障害とは
卵巣の活動が加齢に伴って徐々に弱まり、月経がこない状態が1年間続いた時に、1年前を振り返って「閉経した」と判断します。個人差はありますが、日本の平均閉経年齢は約50.5歳とされており、閉経をはさんだ前後5年間の約10年間のことを「更年期」といいます。
閉経をはさんだ前後5年間の約10年間のことを「更年期」を呼びますが、この時期に卵巣の老化が始まると卵巣から女性ホルモンを十分に出せなくなり、脳と共同で築いてきたホルモンバランスが崩れてしまいます。これに伴って、心身にさまざまな症状が起こってくるものを「更年期症状」と呼びます。
のぼせ・発汗・ホットフラッシュ・動悸・頭痛・めまい・肩こりなどの身体症状や、情緒不安定・イライラ・抑うつ気分などの精神症状が出現することもあり、個人差が大きいです。
「更年期症状」のうち、症状が重く日常生活に支障を来す状態を「更年期障害」と判断します。つまり、「更年期に生じた症状によって日々の生活に辛さや何らかの支障がある」とご自身が感じていれば、それは更年期障害と判断されることになります。
更年期障害についてもっと知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
認知症とは
認知症とは、さまざまな脳の病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に低下し、認知機能(記憶、判断力など)が低下して、社会生活に支障をきたした状態をいいます (1)。
アルツハイマー病はその最も一般的なタイプであり、長い年月をかけて脳にアミロイドβ、リン酸化タウというタンパク質がたまり認知症をきたすと考えられています。
記憶障害(もの忘れ)から始まることが多いですが、
-
失語(音として聞こえていても話がわかりにくい、物の名前がわかないなど)
-
失認(視力は問題ないのに、目で見えた情報を形として把握し難い)
-
失行(手足の動きは問題ないのに、今までできていた動作を行えない)
などが目立つ場合もあります (1)。
ここからは、認知症の中で最も代表的なアルツハイマー病について、女性という性別や更年期障害との関連を解説していきます。
女性とアルツハイマー病
発症頻度
アルツハイマー病の診断を受けている人数は女性の方が男性よりも多く、アメリカでは65歳以上のアルツハイマー病患者530万人のうち、330万人が女性、200万人が男性であると推定されています (2)。また、介護者の3分の2が女性で、その3分の1が娘であるため、アルツハイマー病の負担は女性により大きなものとなっています (2)。
また、45歳時点で、その後にアルツハイマー病を発症する推定リスクは、女性で約5分の1(20%)、男性で10分の1(10%)とされています (3)。
この違いの最も大きな要因は「女性が男性よりも長生きする」ことと考えられていますが、寿命だけではなく他の面も影響していることがわかってきています。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績