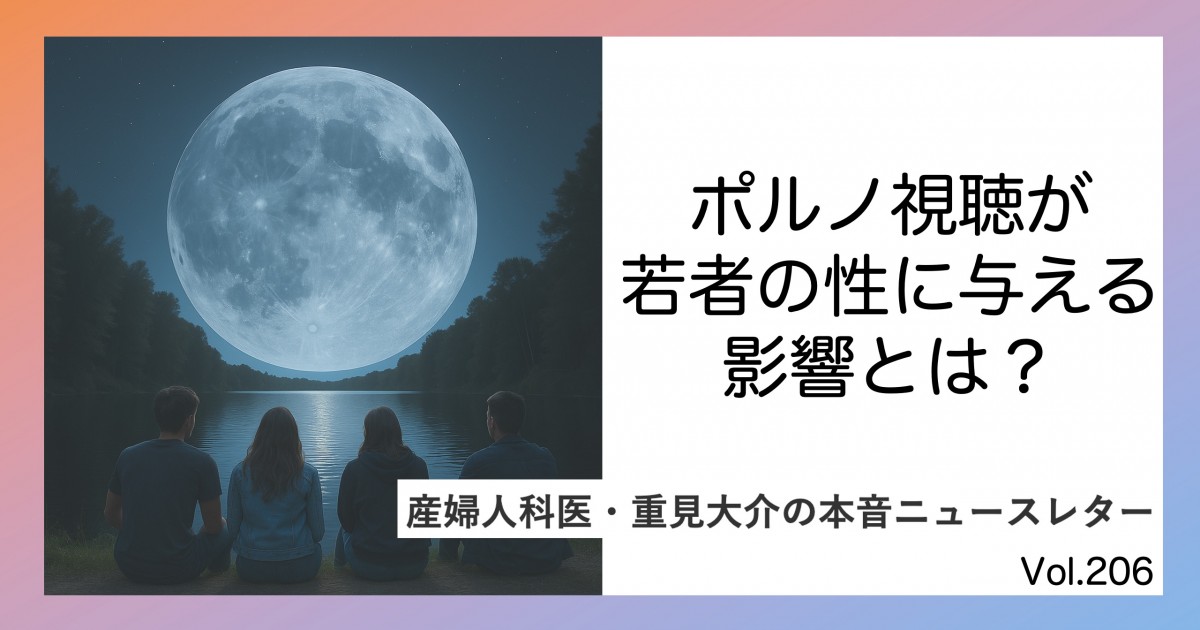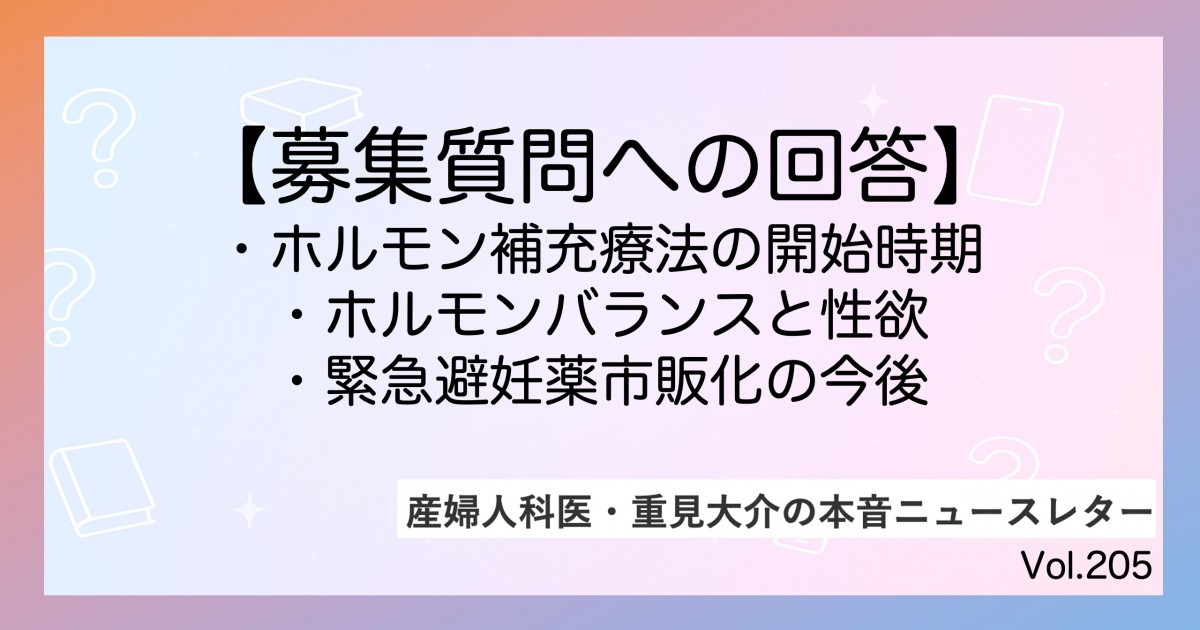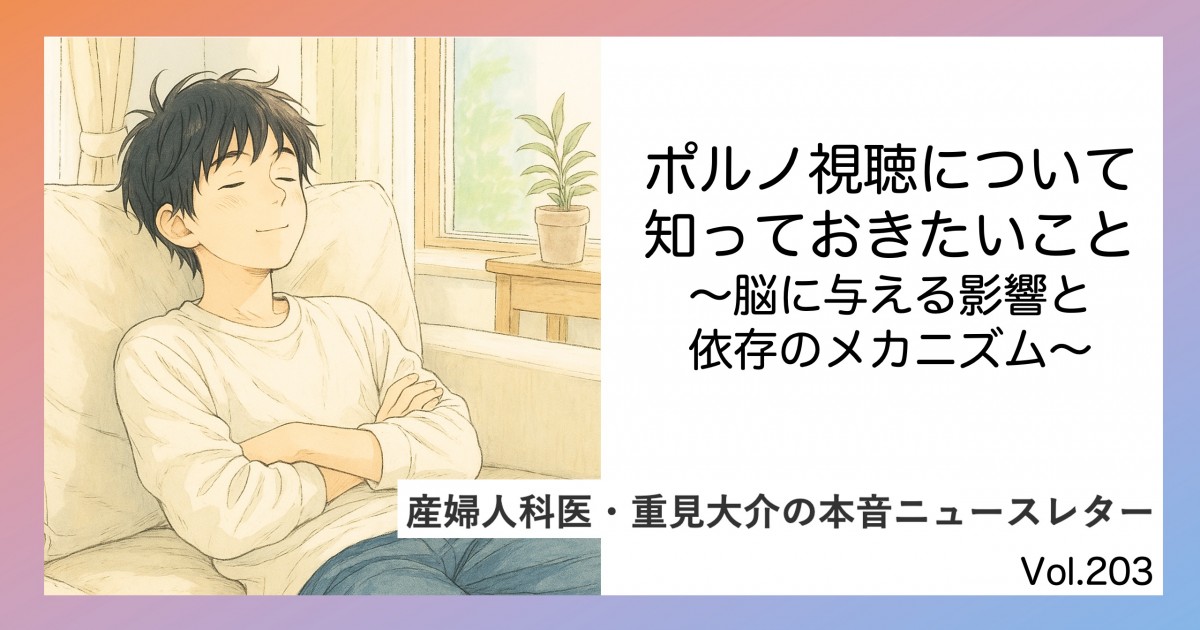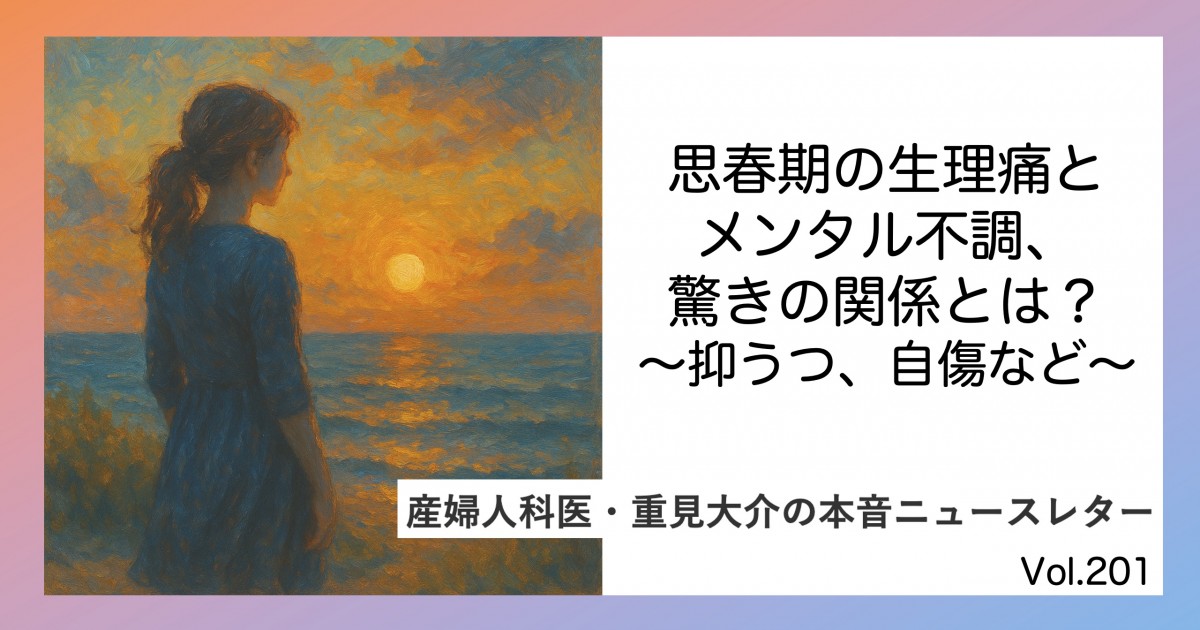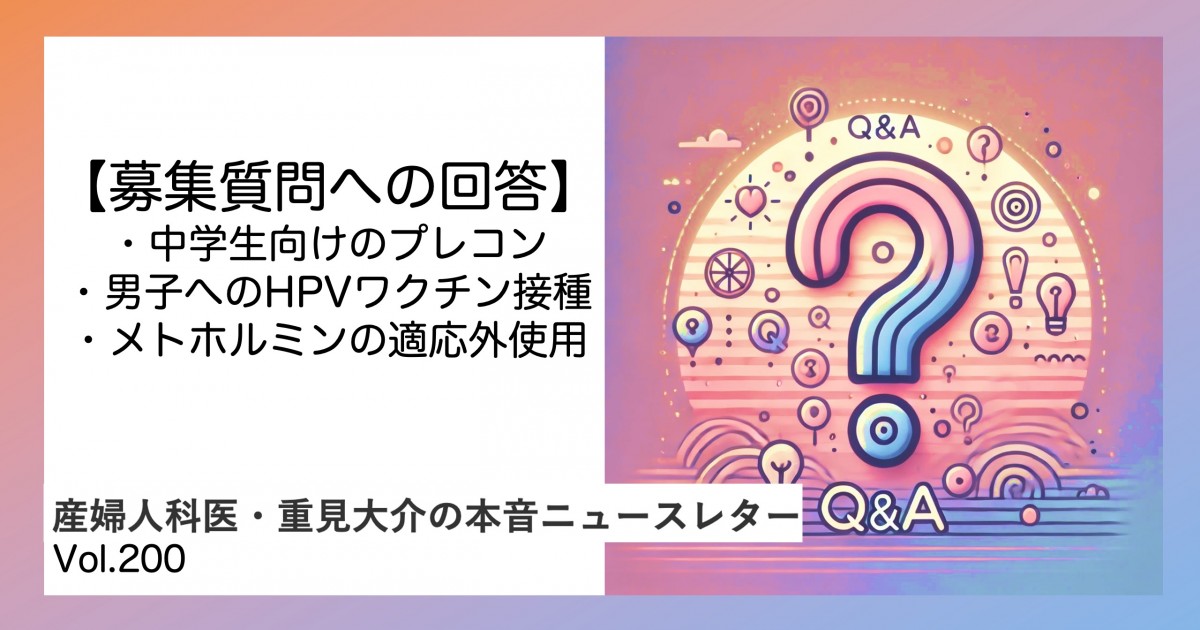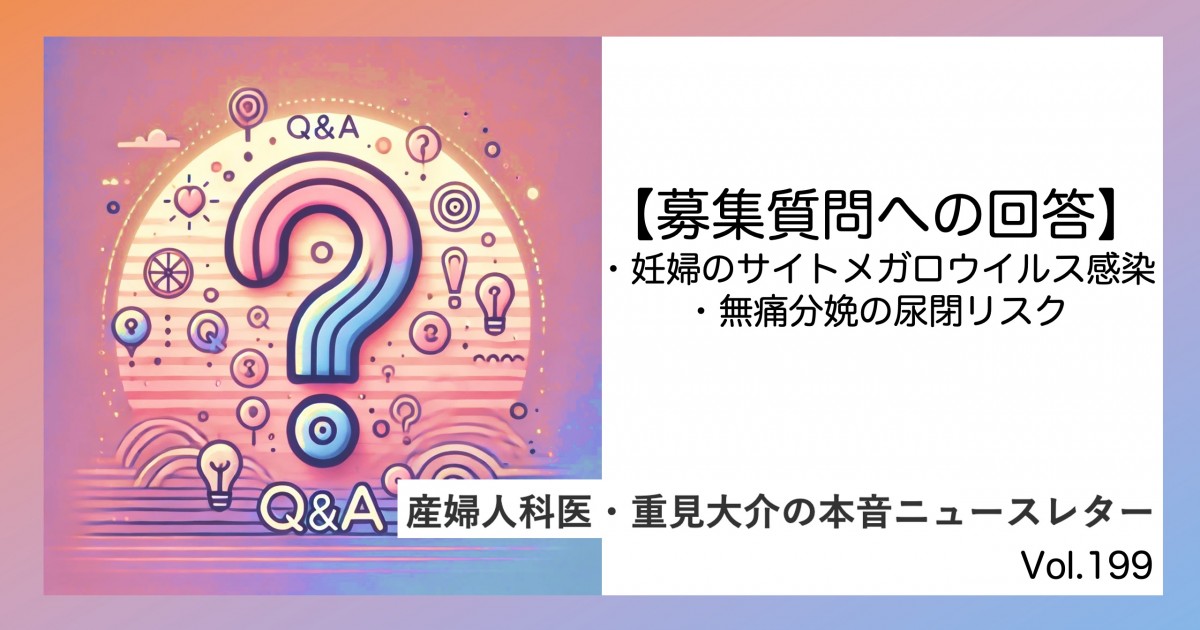帝王切開分娩後の出産プラン:自然分娩か?予定帝王切開か?メリット・リスクを徹底比較
本ニュースレターでは、女性の健康や産婦人科医療に関わるホットトピックや社会課題、注目のサービス、テクノロジーなどについて、産婦人科医・重見大介がわかりやすく紹介・解説しています。「○○が注目されているけど、実は/正直言ってxxなんです」というような表では話しにくい本音も話します。
今回は無料登録で全文読める記事です。メールアドレスをご登録いただくだけで最後まで読むことができます。
帝王切開で出産する割合は増えており、現在、日本では年間4〜5人に1人が帝王切開で出産しているとされています。ただ、帝王切開を経験したのちの出産は特有のリスクを抱えることとなるため、注意が必要です。
本記事ではメリット・リスクを徹底比較し、医学的にわかりやすく解説します。近年の研究結果や診療ガイドラインの内容もご紹介します。
この記事でわかること
-
帝王切開後の出産が特別な理由
-
2つの選択肢:自然分娩の試行(TOLAC)と予定帝王切開(ERCS)
-
最新の研究結果による科学的評価
-
研究の限界点や解釈の注意点
-
日本の診療ガイドラインに書かれている内容
-
マイオピニオン(総合的な私個人の考えや意見)
なぜ帝王切開後の出産は特別なの?
帝王切開分娩は、経腟分娩(自然分娩)が難しい場合に、お腹と子宮を切開して赤ちゃんを取り出す方法です。子宮に一度切開が入るため、たとえその傷が治癒したとしても、次の出産時にはさまざまなリスクを伴うことになります。
以下に、もう少し詳しく書いていきます。
-
子宮瘢痕の存在
帝王切開では子宮筋層を切開・縫合するため、その部位(瘢痕)は次の自然分娩時の陣痛に耐えにくく、子宮破裂のリスク(約0.5~1%未満)が出てきます(これは子宮筋腫などで子宮の切開手術を受けたことのある女性も同様です)。 -
分娩時の管理
経腟分娩を試みる(TOLACと呼ばれます)場合は、陣痛や分娩進行を厳重にモニタリングし、異常時には即座に緊急帝王切開へ移行できる体制が必要です。施設面でも人員面でもかなり充実した体制が求められることになりますね。 -
胎盤異常のリスク
帝王切開の経験があると、「癒着胎盤」と呼ばれるような胎盤異常の頻度が増し、産後の大量出血の危険性が高まることがわかっています。 -
予定帝王切開の考慮
再度、計画的に帝王切開を選択する場合は、前回手術後の経過や胎児の発育、妊娠週数を踏まえ、安全なタイミングで行います。早すぎても胎児に負担がかかりますし、遅すぎて陣痛が来てしまってもダメなので、個々人の状況に合わせてスケジュールが検討されます。
これらの点から、帝王切開後の出産は一般的な初産や通常の経腟分娩とは異なる特別な管理が求められます。
前回の帝王切開の傷は、もちろん自然な治癒力によってくっつくのですが、実は完全に元の厚みに戻らないことも少なくなく、たまに「縫合した部分の子宮が非常に薄っぺらいままで、妊娠後期になるとほぼ紙のような厚さの子宮筋しかない」という恐ろしい状況の方もいらっしゃいます。(私も実際に経験があり、予定帝王切開の際にほぼ透けているくらいの薄さになっていた子宮を見た時は背筋が凍る思いでした。。)
2つの選択肢:自然分娩の試行(TOLAC)と予定帝王切開(ERCS)
帝王切開分娩をしたのち、次回の出産時に経腟分娩を試すことを「帝王切開後経腟分娩の試行(Trial of Labor After Cesarean: TOLAC)」といいます。無事に経腟分娩になった場合には「帝王切開後経腟分娩(Vaginal Birth After Caesarean Section: VBAC)」と呼びます。ややこしいですね。(笑)
過去の研究から、TOLACでは産後出血、産後の子宮内膜炎、分娩時の子宮破裂、輸血の必要性、周産期死亡、および出生児の低酸素性虚血性脳症などのリスクが高いことが示されています。しかし、もしうまく安全に成功すれば、本来陣痛が来る自然なタイミングで出産でき、手術による合併症リスクを避けられるという大きなメリットも存在しています。
予定反復帝王切開(Elective Repeat Cesarean Section: ERCS)は、予定を立てて陣痛が来る前に帝王切開で出産する方法です。言い換えれば、前回も帝王切開分娩をしたことですし、今回も帝王切開分娩でいきましょう、ということですね。これによって、帝王切開歴があることによる経腟分娩(自然分娩)のリスク(主に子宮破裂)をかなり減らすことができるのですが、帝王切開手術それ自体による合併症のリスクはどうしても付きまといます。

Yatharth HospitalsのWebサイトより引用。帝王切開(左図)と経腟分娩(右図)の比較イメージです。
現在は、過去に帝王切開の経験がある女性は、どちらの分娩方法についてもそれに伴うリスク(とメリット)について十分な情報提供を受けることが推奨されています。しかし、実際にはきちんと説明されなかった、という声を耳にすることも少なくないなと感じており、医療従事者にも知識のアップデートや妊婦さんへの説明の場の設定などが必要だよなと考えています。
この記事は無料で続きを読めます
- 最新の研究結果による科学的評価はどうなっている?
- 研究の限界点や解釈の注意点は?
- 日本の診療ガイドラインに書かれている内容は?
- マイオピニオン(総合的な私個人の考えや意見)
すでに登録された方はこちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績