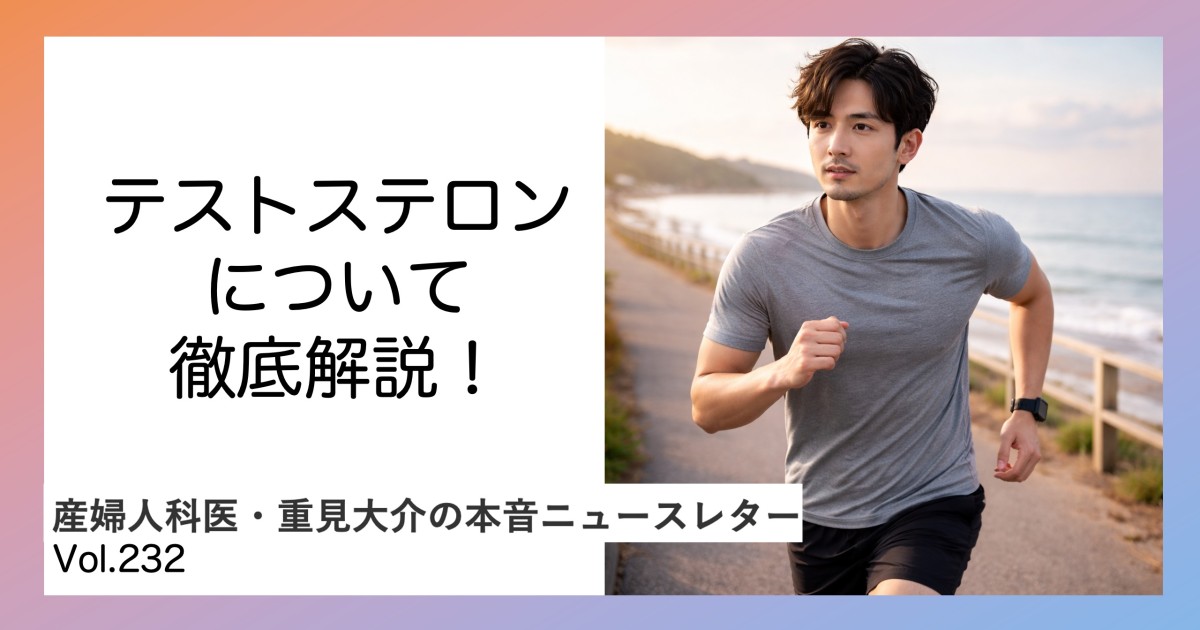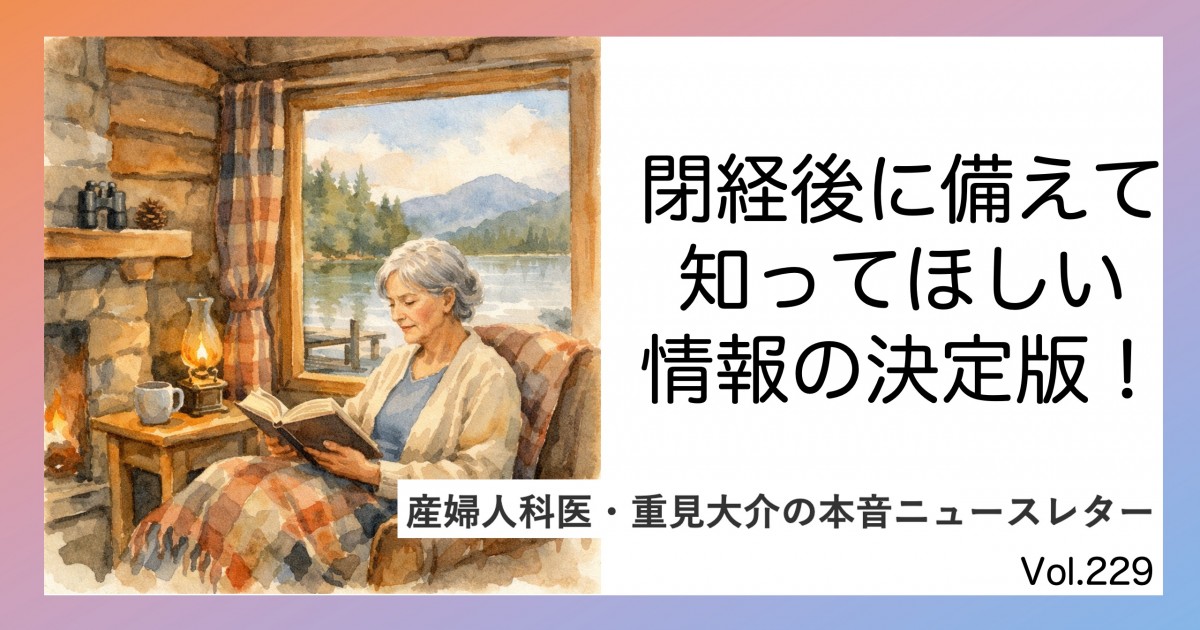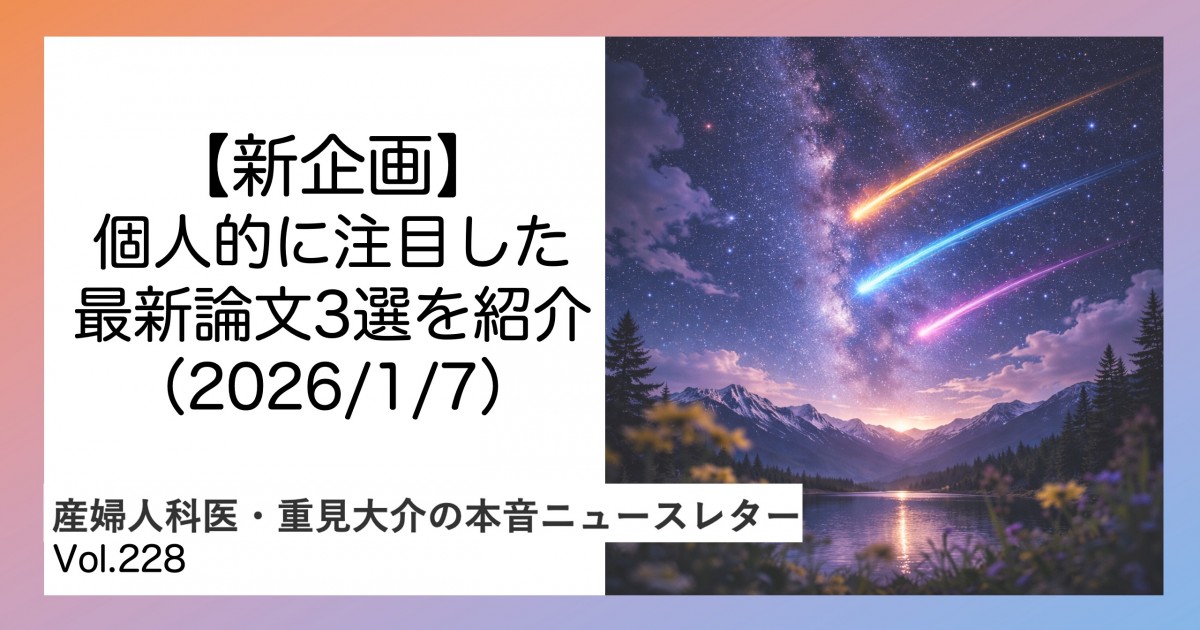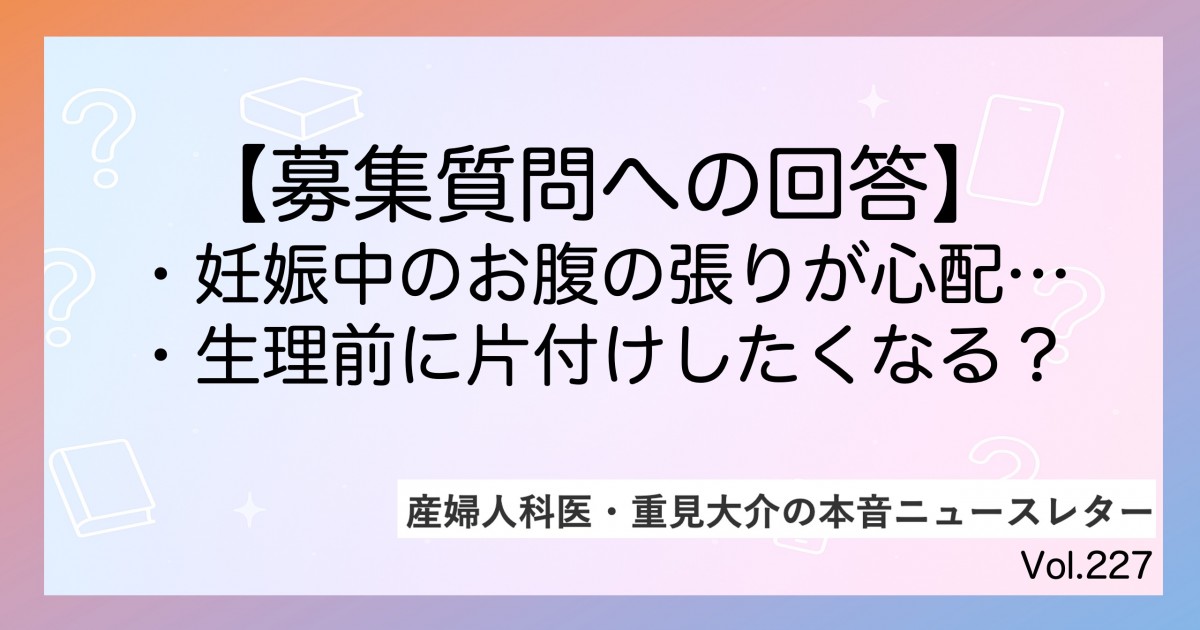【後編】遺伝子や染色体に関する生まれつきの病気って?〜基礎から具体例まで徹底解説〜
今回は遺伝子や染色体に関する生まれつきの病気について解説します。後編では、遺伝性疾患を持って生まれるリスクや遺伝カウンセリング、出生前検査などを解説します。
本ニュースレターでは、女性の健康や産婦人科医療に関わるホットトピックや社会課題、注目のサービス、テクノロジーなどについて、産婦人科医・重見大介がわかりやすく紹介・解説しています。「○○が注目されているけど、実は/正直言ってxxなんです」というような表では話しにくい本音も話します。
今回は無料登録で全文読める記事です。メールアドレスをご登録いただくだけで最後まで読むことができます。
なお、一部の記事(より専門的なもの、私自身の思いを語るものなど)は、サポートメンバー(有料登録読者)に限定してお届けします。サポートメンバー登録いただくと過去の全ての記事を読めるだけでなく、スレッドでの意見交換や、オンライン交流イベントにご参加いただけます。本ニュースレター継続の励みにもなりますので、ご登録いただけると大変嬉しいです。詳細はこちらをご覧ください。
この記事でわかること
-
遺伝性疾患が子どもに起こるリスクが高まるのはどのような場合か
-
遺伝カウンセリングとはどういうものか
-
遺伝カウンセリングを行っている施設を探す方法
-
出生前検査にはどのような種類があるのか
-
スクリーニング検査とはどういうものか
-
確定的検査とはどういうものか
-
新型出生前遺伝学的検査(NIPT)についての詳細
-
出生前検査は受けるべきなのか
-
マイオピニオン(総合的な私の意見・考え)
前回の振り返り
前編の記事では
-
遺伝性疾患とは
-
遺伝子とは
-
染色体とは
-
染色体異常とは
-
遺伝性疾患の種類
などを解説しました。
ダウン症などよく耳にする疾患から、非常に稀な疾患まで、遺伝性疾患には多くの種類があることがお分かりになったことと思います。
今回は、より皆さんに関係の深い話として、遺伝性疾患を持って生まれるリスクや遺伝カウンセリング、出生前検査などを解説していきます。
赤ちゃんが遺伝性疾患を持つリスクはどう上がるの?
実際には、遺伝性疾患を持つ赤ちゃんの多くは「特定のリスク因子がないカップル」から生まれてきます。しかし、カップルのどちらかまたは一方が特定の因子を持っている場合には、それに応じてリスクは高まります。
例えば、次の場合に遺伝性疾患が生じるリスクが高まります。
-
親自身が遺伝性疾患を持っている
-
既に遺伝性疾患を持つ子どもを産んだ経験がある
-
家系に遺伝性疾患がある
また、特定の民族や人種によって発症頻度に差がある疾患もあります。例えば、「嚢胞性線維症」は白人に多く、「マルファン症候群」は国や人種で頻度に差がないと言われています。
なお、最も代表的な染色体異常である「ダウン症候群(21トリソミー)」は、母親の年齢が上がるほど発症リスクが上がります。40歳時点(およそ1%=100人に1人)では25歳(およそ0.08%=1250人に1人)と比べて約10倍の発症頻度となります。
遺伝カウンセリングについて
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績