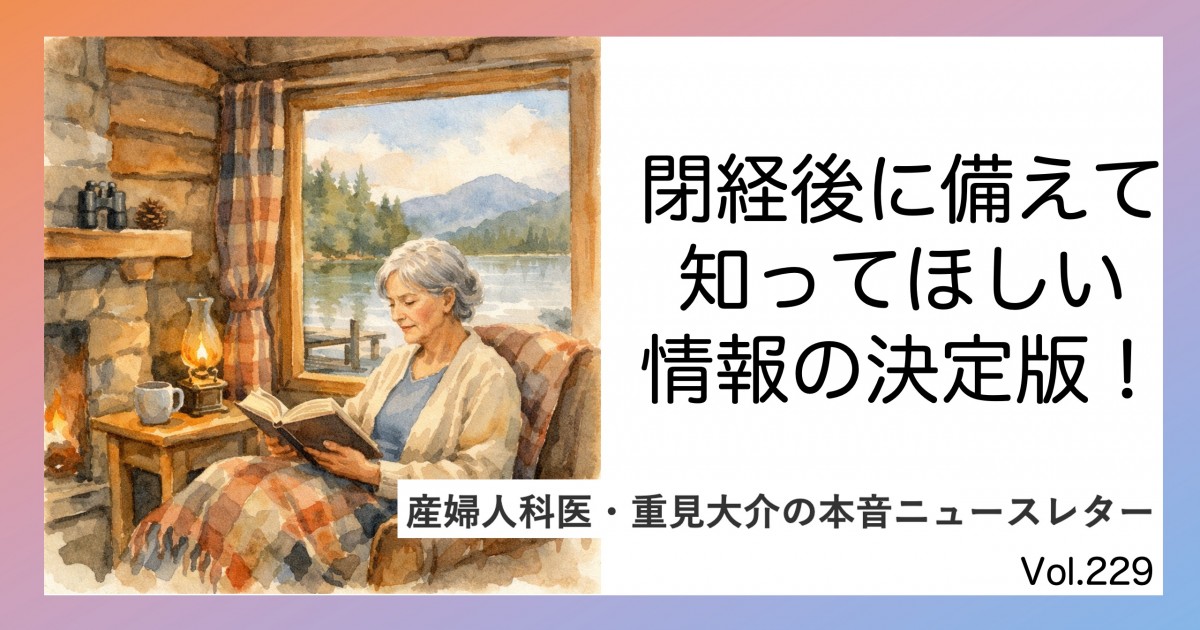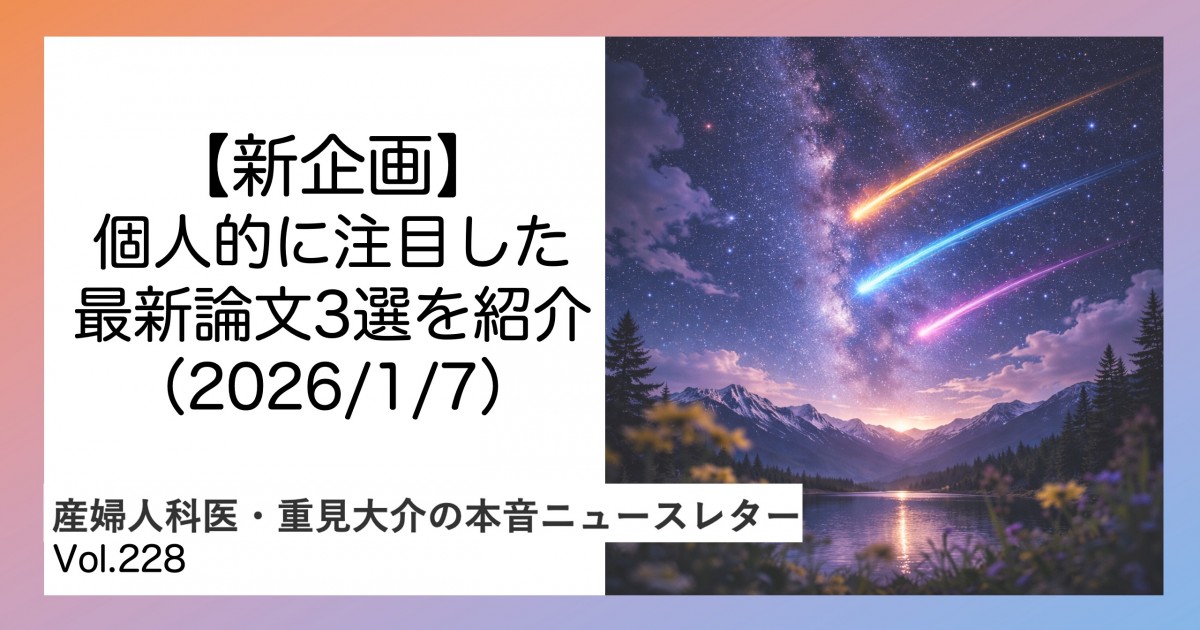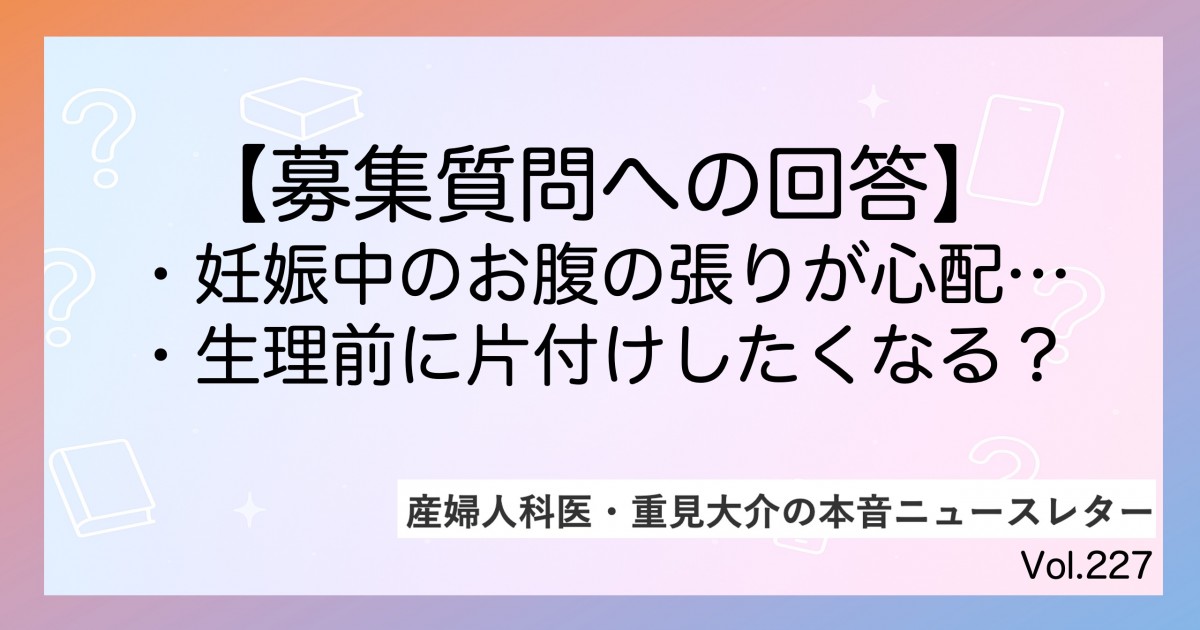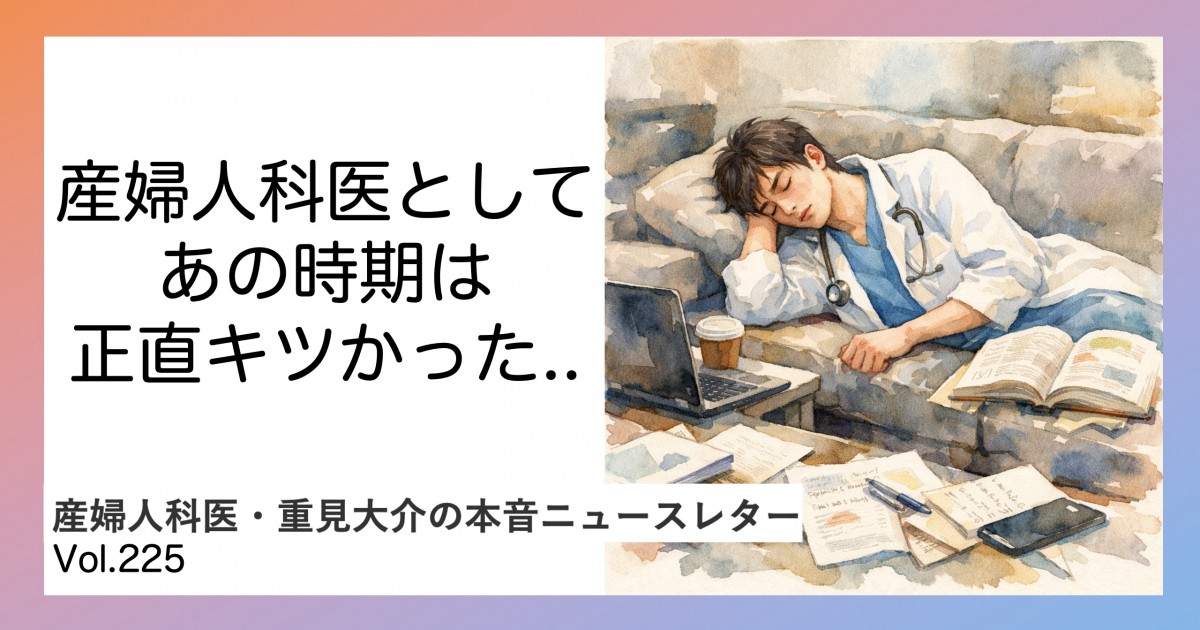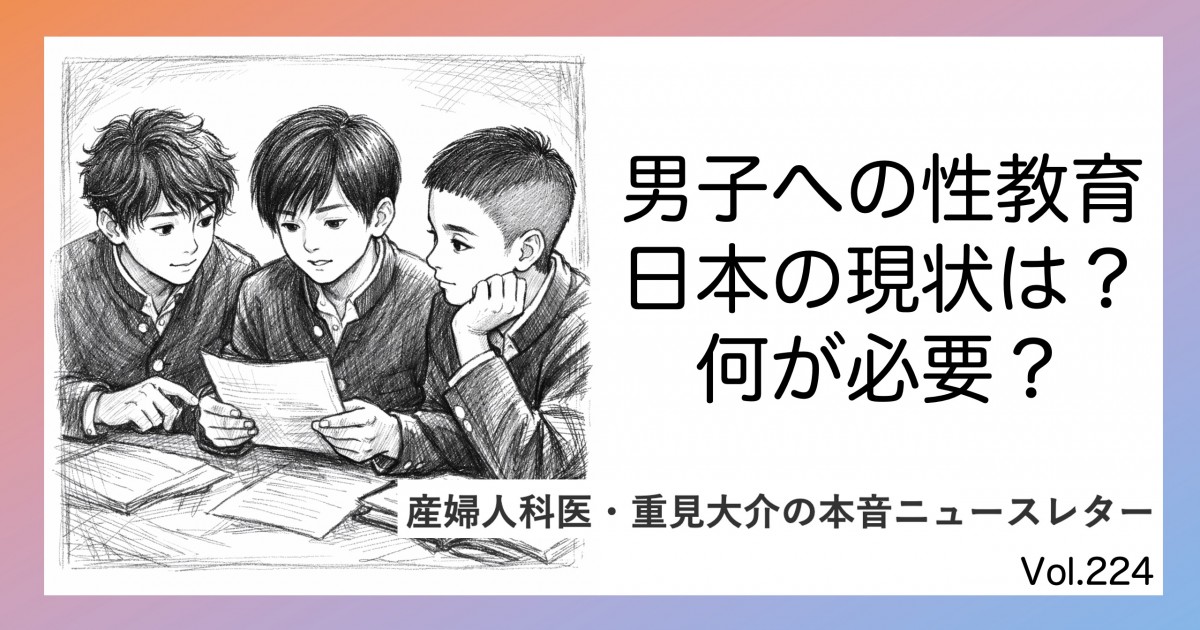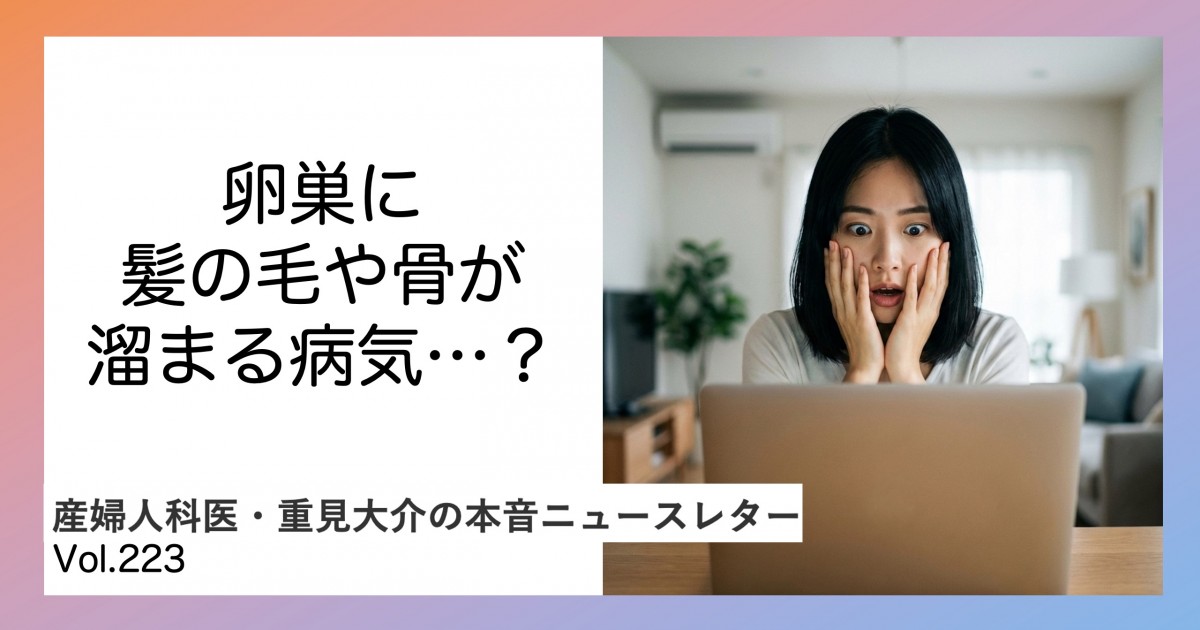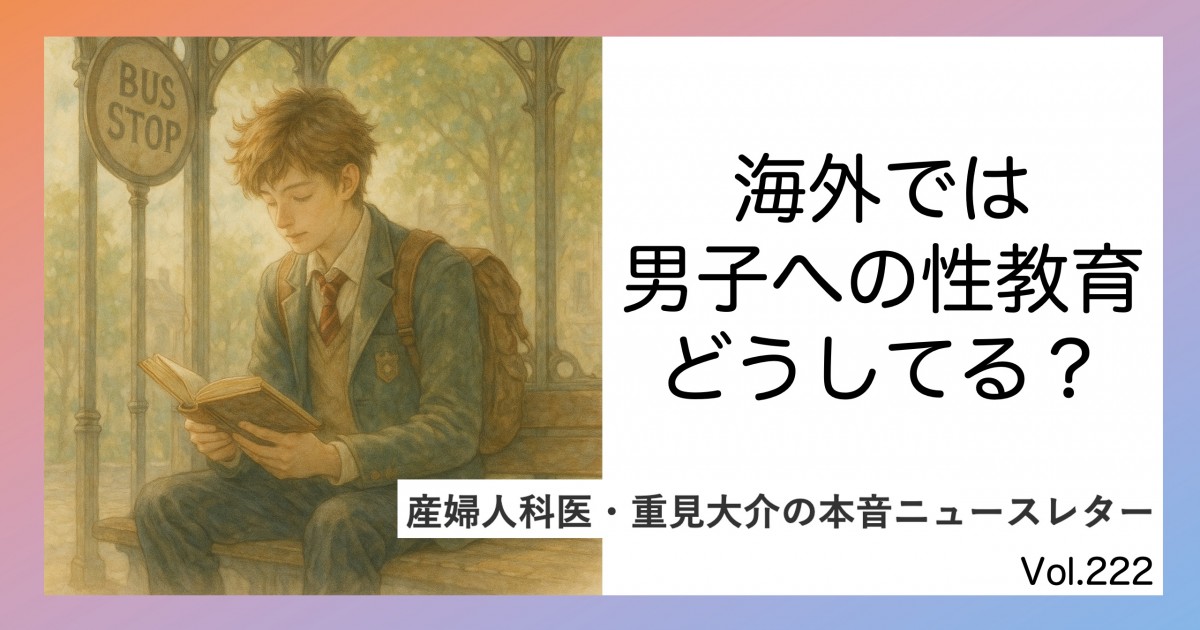女性の健康に役立つ漢方薬!〜具体例から注意点まで総まとめ〜
こんにちは。本ニュースレターでは、女性の健康や産婦人科医療に関わるホットトピックや社会課題、注目のサービス、テクノロジーなどについて、産婦人科医・重見大介がわかりやすく紹介・解説しています。「○○が注目されているけど、実は/正直言ってxxなんです」というような表では話しにくい本音も話します。
詳細は以下をご覧ください。
この記事でわかること
-
漢方薬とはどんなものか
-
どのくらいの種類があるのか
-
女性の健康課題の特徴と漢方薬の相性
-
漢方薬のメリットとデメリット
-
婦人科でよく使われる代表的な漢方薬(婦人科三大処方など)
-
よくある症状への具体的な使用例(冷え性、月経異常、更年期障害)
-
よくある誤解Q&A5つ(漢方薬はすべての病気に効果がある?、漢方薬は副作用がない?、漢方薬は即効性がない?、漢方薬と西洋医学の薬は一緒に使ってはいけない?、漢方薬は安全なため誰でも使える?)
-
妊婦さんが使う場合の安全性について
-
マイオピニオン(総合的な私個人の考えや意見)
漢方薬の基本
まず、漢方薬とはどのようなものか、基本を確認しておきましょう。
漢方薬は生薬を原料にできた薬で、生薬は草や木、動物や鉱物など、自然に存在しているものになります。漢方薬の多くは2つ以上の種類の生薬を組み合わせて作られており、「その人の症状を根本から改善していく」ことを目指すものです。東洋医学の1つという位置付けです。
現在、日本の病院や薬局等で手に入る漢方薬は、長い年月をかけて生薬の種類や量、組み合わせが工夫・検討され、処方薬や市販薬として確立されたものになります。特定の診断がつけば保険適用されるものもあります。日本では2022年の時点で、医療用漢方製剤(医師が処方し健康保険が適用されるもの)として148種類、一般用漢方製剤(薬局やドラッグストアで市販されているもの)として294種類が存在しています。
漢方薬では、医療用と一般用の製剤に成分上の違いはなく、基本的に「どちらも同様の効果が期待できる」と考えてOKです。
剤型としては、主に「粉薬」と「錠剤」がありますが、全ての種類の漢方薬に両方の剤型があるわけではありません。
西洋医学と東洋医学の違い
西洋医学では聴診や触診、採血検査、画像検査などで生体情報を客観的に収集することで、どの臓器に異常があるかを評価し、特定の診断名を付けることがベースになります。
一方、東洋医学では、生体は「気・血・水」の3要素が体内を循環することによって構成されていると考えます。
-
気:活力・生命機能を維持するエネルギー
-
血:生命を物質的に支える流れ(機能は血液やホルモンに近い)
-
水:潤い(体液、汗、唾液、消化管液など)
何らかの症状が出ている場合、上記の3要素のバランスが崩れていたり、いずれかの要素に異常が生じていると考えます。
女性の健康課題の特徴と漢方薬の相性
女性のライフステージは、女性ホルモンの影響を中心として、年代ごとに状況が大きく変わりやすいという特徴があります。
特に思春期から更年期の不調は、女性ホルモンの揺らぎが背景にあることが多く、
-
急激に女性ホルモンが上昇する思春期
-
急激に減少していく更年期
-
妊娠中や授乳中
-
1ヶ月の中でのホルモン変動
など、さまざまな状況に置かれています。
こうした変動は、ホルモン分泌や自律神経、免疫状態のバランスの崩れやすさにもつながります。また、血管や血流へ影響が及べば血液循環が悪くなって冷え症となり、さらなる不調を引き起こすこともあります。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績