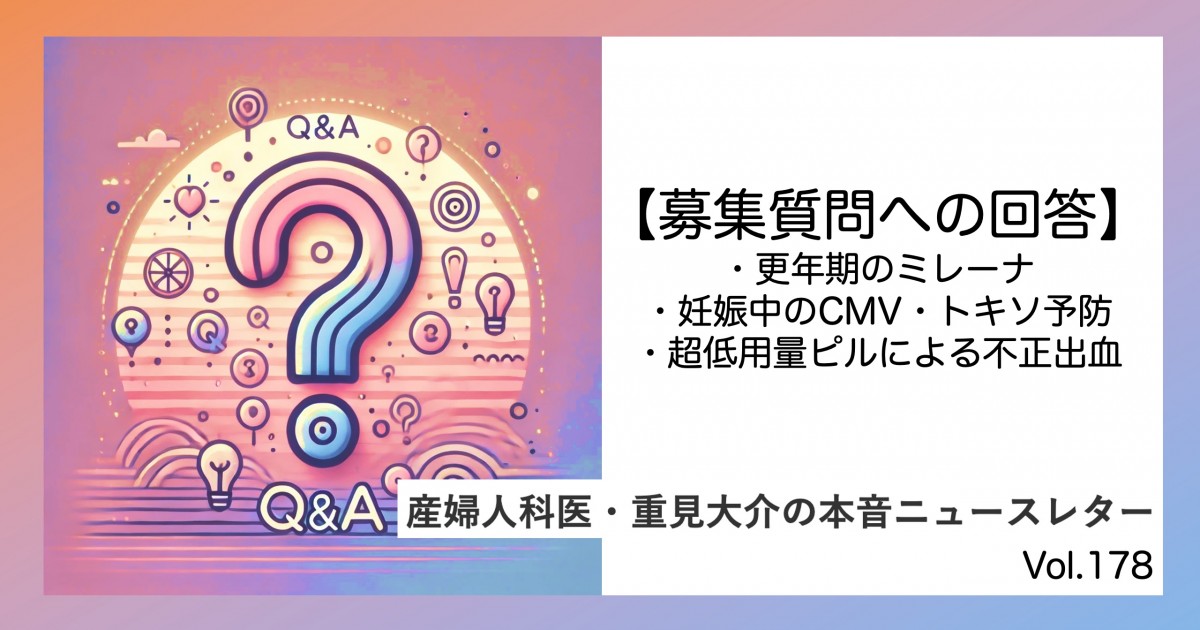私たちが子どもにできること 〜非認知能力についての考え方〜②
こんにちは。本ニュースレターでは、女性の健康や産婦人科医療に関わるホットトピックや社会課題、注目のサービス、テクノロジーなどについて、産婦人科医・重見大介がわかりやすく紹介・解説しています。「○○が注目されているけど、実は/正直言ってxxなんです」というような表では話しにくい本音も話します。
詳細は以下をご覧ください。
今回は「有料登録者限定」のニュースレターです。
この記事でわかること
-
非認知能力向上のために、幼児期の介入をどうしたら良いのか
-
非認知能力の向上に役立つ、家庭と家庭以外の環境作り
-
インセンティブを与えることは効果的なのか
-
子どものモチベーションを上げるための効果的な方法とは
-
マインドセット(心のありよう)の大切さ
-
マイオピニオン(総合的な私個人の考えや意見)
前回の記事のおさらい
前回の記事では、「非認知能力(non-cognitive skills)」、つまり物事に対する考え方、取り組む姿勢、粘り強さ、誠実さ、自制心、楽観的思考など、日常生活・社会活動の様々な面で大きな影響を与える能力について、その重要性、捉え方、親としての関わり、子どもにとってのストレス・トラウマの長期的影響などを紹介しました。
「非認知能力の重要性」について、様々な意味での「貧しさ」を感じている若者世代が増えてきている日本で、非認知能力の高い子どもの方が学歴が高く、健康状態が良く、シングルペアレントになる可能性は低く、借金を抱えたり犯罪をおかしたりする可能性が低いというデータについて触れました。
また、「非認知能力」をどう捉えるかについて、認知能力と同じような「スキル」としては考えない方が良いということを書きました。つまり、「非認知能力は教えることのできるスキル」と考えるよりも、「非認知能力は子どもを取り巻く環境によって育まれるもの」と考えた方がより正確だし有益と考えられています。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績