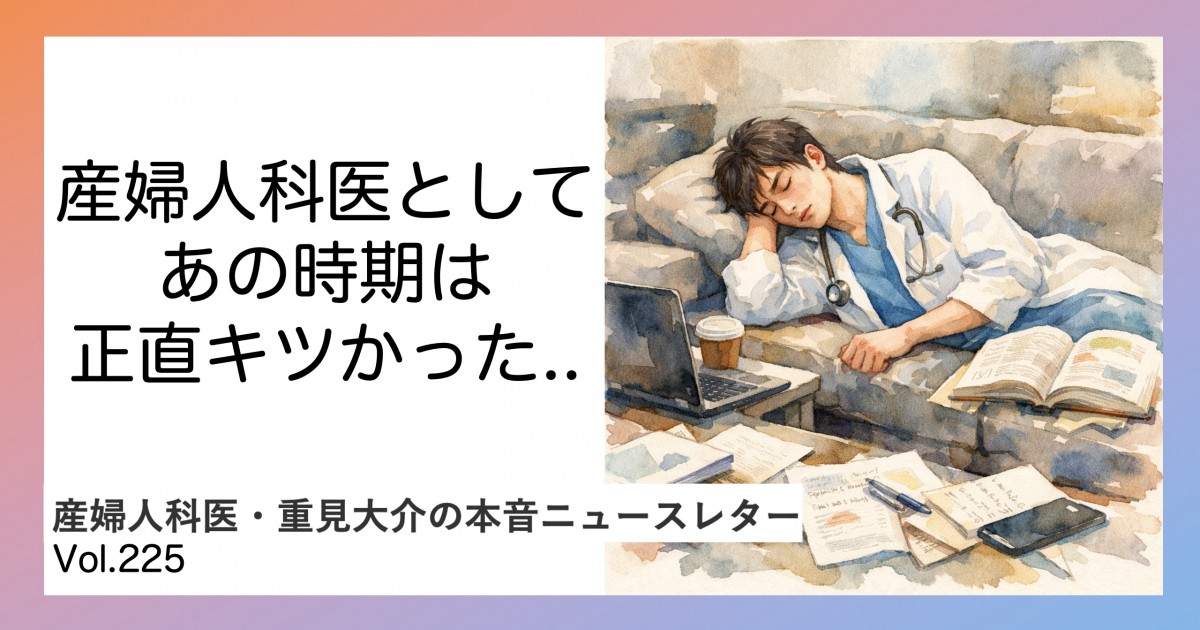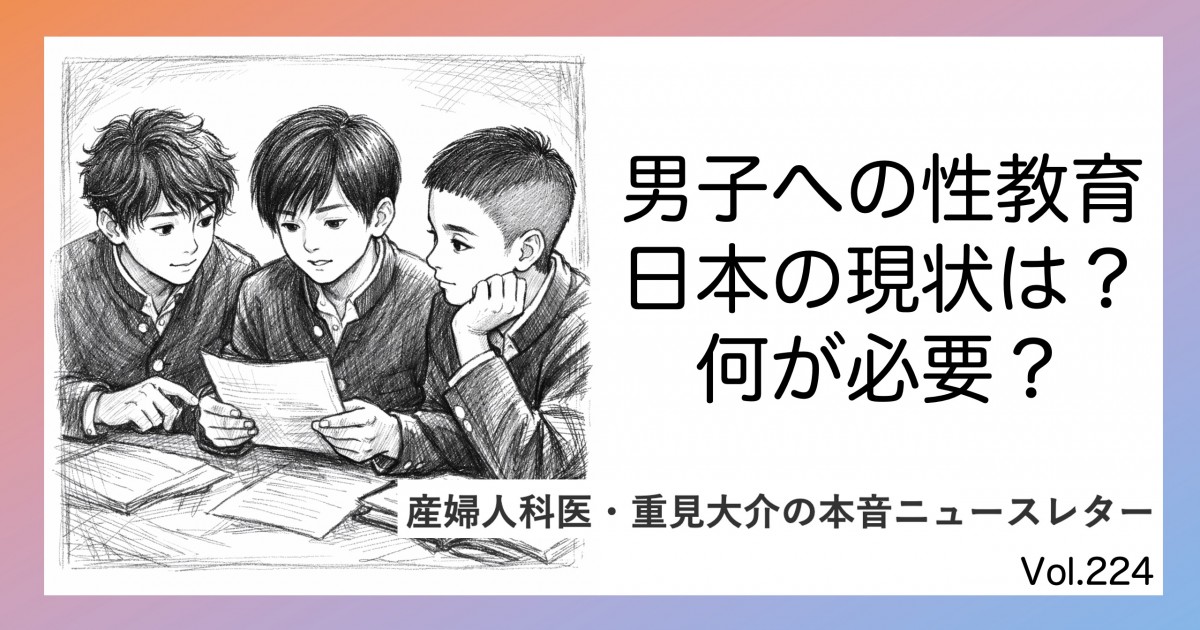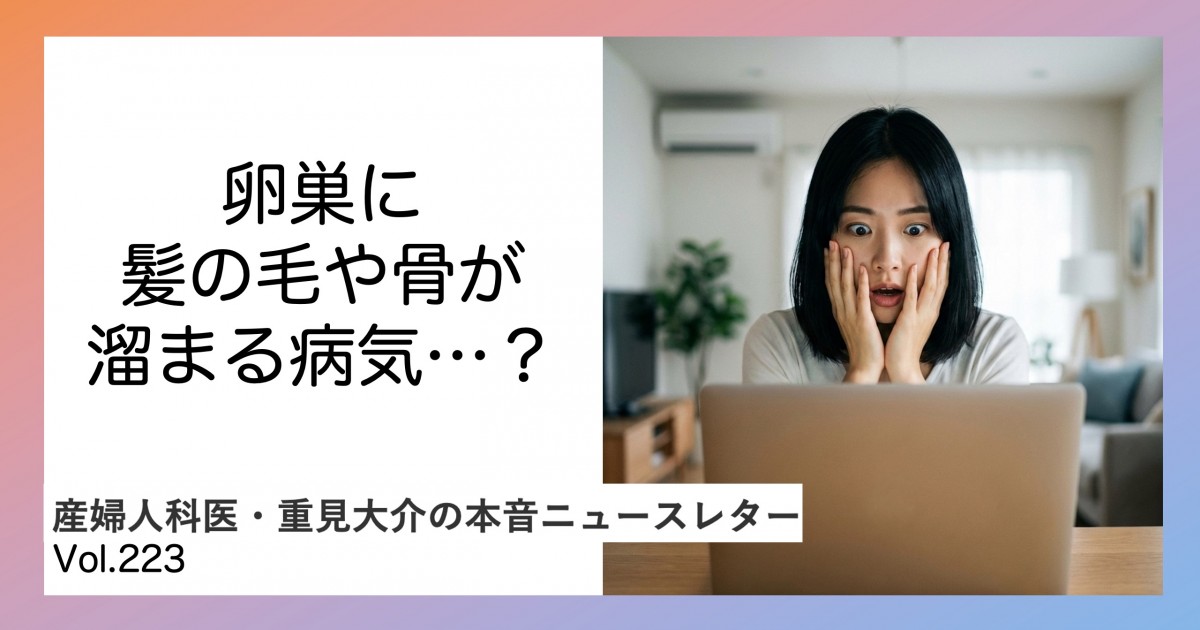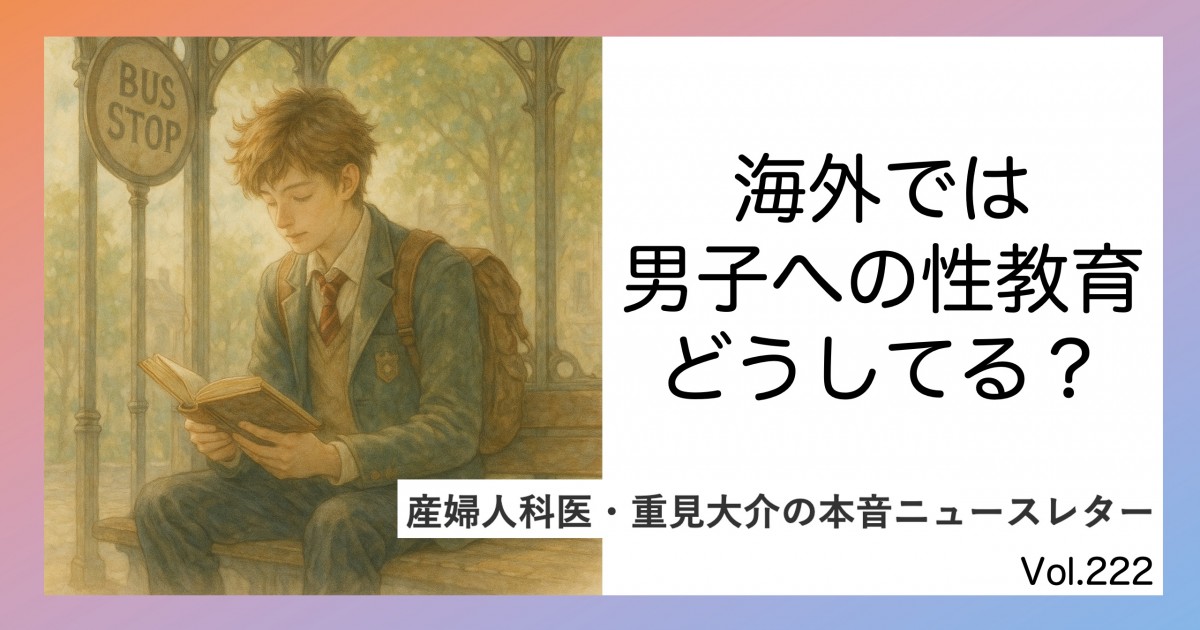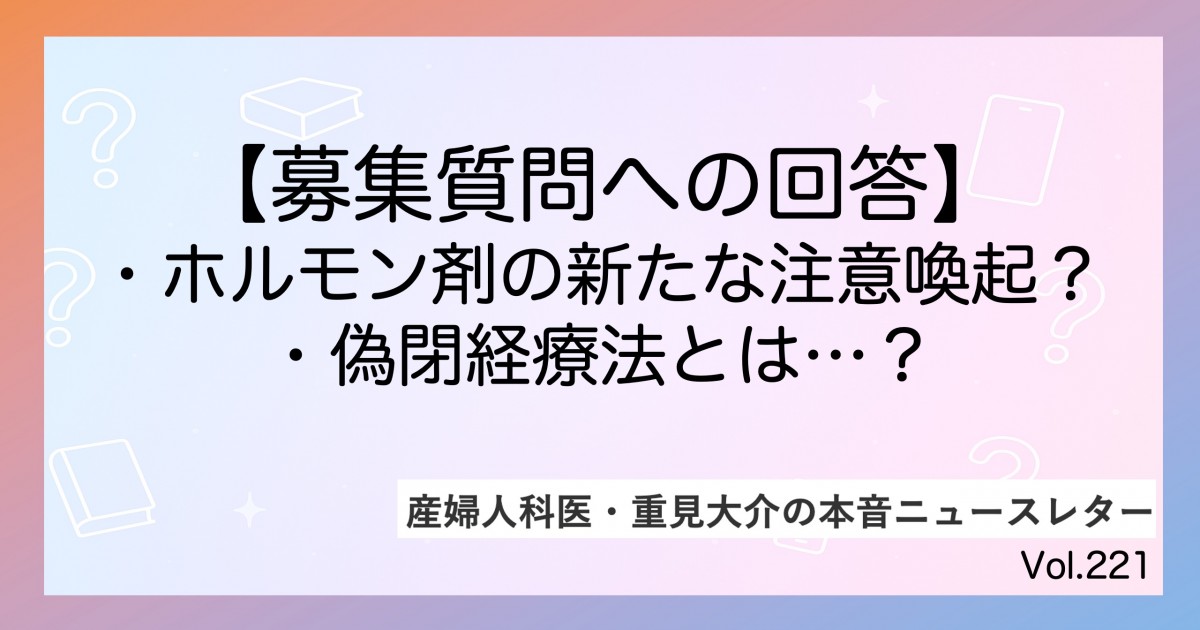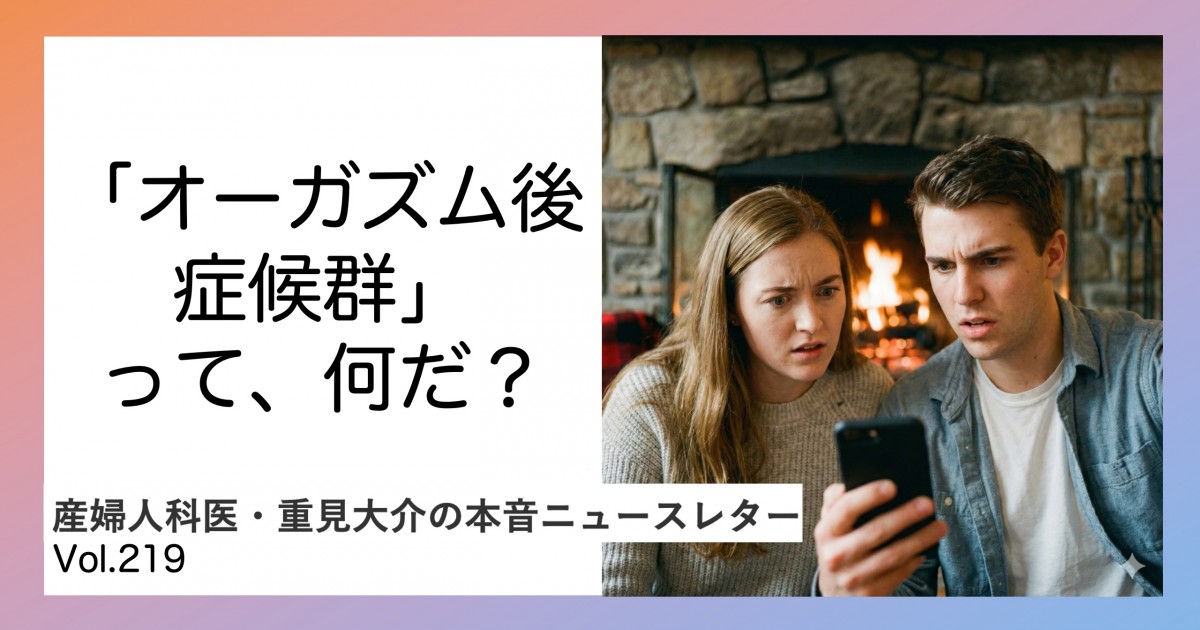性教育シリーズ(9) 〜男性のSRHR〜
本ニュースレターでは、女性の健康や産婦人科医療に関わるホットトピックや社会課題、注目のサービス、テクノロジーなどについて、産婦人科医・重見大介がわかりやすく紹介・解説しています。「○○が注目されているけど、実は/正直言ってxxなんです」というような表では話しにくい本音も話します。
今回はサポートメンバー限定記事です。最後までご覧になりたい方はサポートメンバー登録をお願いいたします。
*年末年始特別企画として、2026/1/5まで期間限定で無料登録の皆様にも公開中です。

性と生殖に関する健康と権利(SRHR: Sexual Reproductive Health and Rights)についてメディアで目にすることも増えてきましたが、当然これは女性だけのものではありません。男性にとっても非常に重要なテーマです。
これまでの性教育では、どうしても「妊娠や出産は女性の問題」として扱われがちでした。しかし、避妊や家族計画、性感染症の予防、パートナーシップなど、男性が主体的に取り組むべき課題はたくさんあります。また、男性特有の身体の仕組みや悩みはもちろん、「男性らしさ」という社会的なプレッシャーが原因となって、適切な知識を得にくい側面もあります。
今回は性教育シリーズの第9回目として、まず SRHR の基本概念を整理したうえで、男性に焦点を当てた5つのポイントについて解説します。さらに、性教育の一環として子どもに伝える(話す)ときのコツと、具体的な言葉かけの例も紹介します。性に関する話題は、親子であっても話しにくいことが多いかもしれませんが、将来的に子ども自身が自分の身体を大切にし、相手との関係を尊重して生きていくための基礎となる大切な学びです。ぜひ最後までお読みいただき、ご家庭や学校現場などでのコミュニケーションの一助になれば幸いです。
この記事でわかること
-
「SRHR」とはどういうものか
-
男性のSRHRにおける5つのポイント
-
子どもに伝えるときの4つのポイント
-
具体的な伝え方の例
-
日常生活で伝える・考えてもらうための工夫や取り組み
-
将来の仕事でも役立つ場面や理由
「SRHR」とはどういうものか?
SRHR とは「性と生殖に関する健康と権利」のことで、世界保健機関(WHO)や国際連合人口基金(UNFPA)などで定義・推進されている概念です。具体的には、以下のような内容を含みます。
-
性的健康(Sexual Health): 安全で満たされた性行為ができる状態や、性的関係における身体的・精神的健康が守られること
-
生殖に関する健康(Reproductive Health): 妊娠、出産、家族計画など、妊娠や出産に関わる健康が十分に保証されること
-
権利(Rights): 誰もが差別されることなく、性や生殖に関して自分の意思で決定できること、また必要な情報や医療を受けることができること
日本では、性教育の場面で「SRHR」という言葉自体はまだあまり一般的ではないように感じています。しかし近年は、セクシュアルマイノリティの方や、そのほか多様な家族のあり方が社会に広く認知されるようになり、性や生殖に関する問題がより多角的に議論され始めています。
この概念は女性だけにとどまらず、男性やあらゆるジェンダーの人々にとっても重要です。例えば、男性に関しては、健康的な性機能の維持や避妊への主体的な関与、パートナーとのコミュニケーションを通じた責任ある行動などが含まれます。また、地域や文化によっては「男性は自分の悩みを打ち明けにくい」といったような社会的背景もあり、その意味でも SRHR に基づく包括的なアプローチが欠かせません。
この記事は無料で続きを読めます
- 男性のSRHRにおける5つのポイントとは?
- 子どもに伝えるときの4つのポイント
- 具体的な伝え方の例
- 日常生活で伝える・考えてもらうための工夫や取り組み
- 将来の仕事でも役立つ場面や理由
すでに登録された方はこちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績